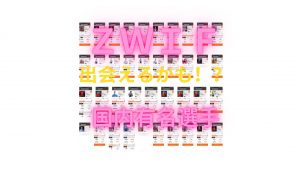ロードバイクが速くなるためのカフェイン摂取のメリット・デメリット・適正量と効果
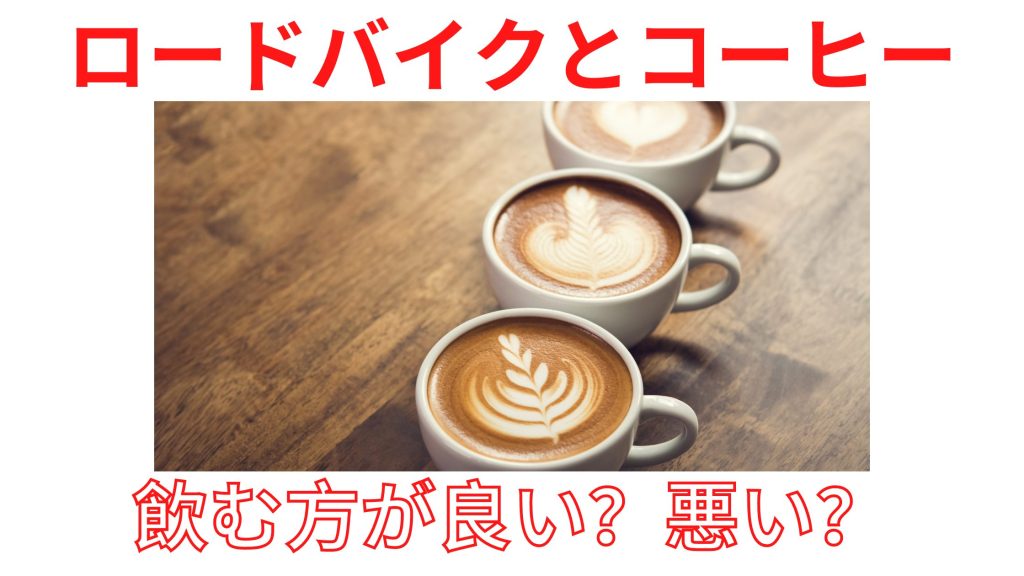
Contents
目次
コーヒー=カフェイン摂取
トレーニング前のコーヒーはあり?なし?
ロードバイクとコーヒーは相性が良く、トレーニン前に1杯飲む人も多いです。
トレーニングの目的地が、コーヒーショップであることもしばしばです。
プロ選手も、レース前に飲んだりします。
ロードバイクの補給食についてはこちらの記事を参考に
ロードバイクの前にコーヒーを飲むとトレーニングに良い効果があるとする研究結果がいくつかあります。
カフェイン摂取は、心臓や中枢神経を刺激する効果があります。
適切に摂取すれば、パフォーマンスを向上させることができます。
コーヒーやサプリメントからカフェインを摂取する方法は、多くのプロロードレーサーが取り入れています。
コーヒー・エナジードリンクに含まれるカフェイン
コーヒーのカフェイン含有量
レギュラーコーヒー1杯あたりのカフェイン含有量は約70mgです。
エスプレッソなら60mgから80mgです。
豆でもインスタントでも、カフェイン含有量は大きく違いません。
ドリップ方法によるカフェインの違い
コーヒー豆から煎れる場合、ドリップ方法によってカフェインの量が違います。
| 抽出方法 | カフェイン含有量(237ml) |
| 自動ドリップ | 145mg |
| 手入れドリップ | 125mg |
| エスプレッソ | 50mg~75mg(30ml) |
エナジードリンク・緑茶に含まれるカフェイン
カフェインはコーヒーだけでなく、お茶や紅茶、チョコレート、ココア、コーラ、エナジードリンクにも含まれています。
カフェイン含有量の多いのは緑茶です。
緑茶はカップ1杯で約230mgのカフェインを含みます。
紅茶のカフェイン含有量はコーヒーの半分です。
最近では、ダイエット効果を謳ったカフェイン入り石鹸も販売されています。
石鹸などに含まれるカフェインは、皮膚から吸収されないので全く無意味です。
レッドブルなどのエナジードリンクの危険性がよく言われますが、カフェインの含有量は多くありません。
エナジードリンクのカフェインの含有量は、1缶あたり80mgから180mgです。
缶コーヒーは多いもので150mgあります。
とりたててエナジードリンクのカフェインの含有量が多いとは言えません。
危険なのはその飲み方です。
アルコールと一緒に飲むと、自分がどれくらい酔っているかが分からなくなります。
その結果、アルコールを過剰摂取したり、カフェインの利尿作用により脱水症状を引き起こしたりします。
アルコールについてはこちらの記事を参考に
【ロードバイクトレーニング】飲酒は悪いが強くなる!?【アルコール】

カフェインがロードバイクに与える影響
カフェインは精神刺激薬
コーヒーに含まれるカフェインは、覚醒作用のある精神刺激薬です。
世界で最も広く使われている精神刺激薬です。
飲料水メーカーは安全だと言い、カフェイン否定派は危険な有機物だと主張します。
カフェインはドーピング!?
カフェインはアンチ・ドーピング規定に定められる禁止リストに指定されていません。
しかし、興奮作用をもたらすので監視リストに入っています。
興奮によりパフォーマンスが向上することが生理学的にも証明されている所以です。
ドーピングについてはこちらの記事を参考に
【サイクルロードレースの次世代ドーピング】遺伝子ドーピングとは!?
適量のカフェイン摂取はパフォーマンスを高める
カフェインを適切に摂取すると、パフォーマンスが向上するとする研究結果が多くあります。
カフェインは、脳のアデノシン受容体と結合し、アデノシンをブロックします。
アデノシンは、休養や睡眠が必要なときにほかの脳信号を抑制する働きがあります。
その結果、カフェインは交感神経を活性化します。
交感神経の活性化により、アドレナリンの分泌が促進されます。
アドレナリンにより、脳内でドーパミンが分泌されます。
心拍数が増加し、血管が拡張します。
心拍数についてはこちらの記事を参考に
一定ペースでロードバイクを漕いでも心拍数が上り続ける「心拍ドリフト」の抑制方法とトレーニングへの活用
カフェインに脂肪分解効果はない
30年前の研究では、カフェインは脂肪分解を活性化させるとされていました。
現在では、この考えは否定されています。
カフェインを摂取すると、交感神経が活性化するものの脂質の代謝に変化は見られませんでした。
カフェイン摂取による筋グリコーゲンの節約効果については、研究により差があり、はっきりしていません。
カフェイン摂取効果の持続時間
コーヒーを飲んだ後は、2時間程度効果が持続します。
効果が表れるまでの時間は約30分です。
トレーニングに行く30分前にコーヒーを飲むと効果的です。
ロードバイクが速くなるためのカフェイン摂取法
適正量は個人差が大きい
カフェインの影響は個人差が大きいことが分かっています。
普段からカフェインを摂取するか否かで、効果が大きく違います。
カフェインの適量は体重1kgあたり3mgから6mgです。
体重60kgの人なら180mgから360mgです。
コーヒー3杯程度に相当します。
過剰摂取はパフォーマンスを低下させる
カフェインの過剰摂取はパフォーマンスを低下させます。
体重1kgあたり9mgを超えると、パフォーマンスが低下します。
胃腸障害、動悸、頭痛が現れるリスクがあります。
日常的にコーヒーを飲まない人は、カフェインの影響が大きくなります。
カフェインの摂取が体重1kgあたり9mgを超えなくても、このような症状が出現する可能性があります。
カフェイン摂取のタイミング
カフェイン摂取の最も一般的なタイミングはレース開始の1時間前です。
レースは長時間に及ぶ場合は、レースの最重要局面が予想される前に摂取することが有効です。
炭水化物・クレアチンとカフェインの同時摂取
ロードバイクの補給に最も重要なのは炭水化物です。
補給についてはこちらの記事を参考に
ロードバイクの補給食・炭水化物補給にベストな選択 安価で使いやすい「粉飴」を徹底解説
何度もアタックがかかる場面では、クレアチンも有効です。
カフェインと炭水化物の同時摂取は、グリコーゲン再合成を速めるとする研究があります。
カフェインと炭水化物を同時摂取してもグリコーゲン再合成に影響を与えないとする研究もあります。
カフェインと炭水化物の同時摂取が、グリコーゲン再合成に悪影響がある可能性は低いと考えられます。
クレアチンとカフェインの同時摂取は、それぞれのメリットを打ち消すとのデータがあります。
クレアチンとカフェインの同時摂取は、慎重に行った方が良いでしょう。
クレアチンとカフェインは別々に摂取したほうが、それぞれのメリットを活かすことができます。
クレアチンについてはこちらの記事を参考に
【ロードバイク】クレアチンリン酸を増やし、繰り返されるアタックやゴールスプリントに勝てる体になる方法【反復スプリント】
カフェインとガンの関係性
カフェインとがんとの関連性が指摘されることがあります。
下の表にあるように、カフェインはがんとは関連性がないか、むしろ危険度を軽減させます。
| ガンの部位 | 増減 | ガンの部位 | 増減 |
| 卵巣 | ⇔ | 胃 | ⇔ |
| 膵臓 | ⇔ | 肝臓 | ↓ |
| 膀胱 | ⇔ | 乳房 | ↓ |
| 結腸直腸 | ↓ | 全部位 | ↓ |
| 肺 | ↑ |
しかし、カフェインの過剰摂取は危険です。
全ての物質は過剰摂取により毒になります。
水でさえ過剰に摂取すると死亡します。
毎日1杯のコーヒーを飲むなら健康に害はありません。
コーヒーを飲むことのデメリット
コーヒーで脱水になる?
コーヒーには利尿作用があります。
そのため、脱水につながるイメージがあります。
しかし、カフェイン摂取による脱水の可能性は低いです。
その理由は、カフェインは飲料に含まれるため、水分も同時に摂取するからです。
運動前に100mgから600mgのカフェイン(缶コーヒー4本分)を摂取しても水ー電解質バランスは崩れなかったとの実験結果もあります。
別の研究では、60名の男子大学生が運動前にカフェインを摂取しても水分と電解質のバランスは崩れませんでした。
コーヒーの常識的な摂取量では、身体に害はありません。
販売されている飲料のカフェイン含有量は次のとおりです。

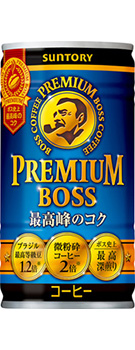


コーヒーを飲むとトイレが近くなります。
個人差がありますが、レース中にトイレに行きたくない人はコーヒーを控えた方が良いかも知れません。
日常的にカフェインを摂取している人は、この傾向が低くなります。
脱水についてはこちらの記事を参考に
カフェインが切れた時の影響
カフェインの効果が持続する時間は2時間程度です。
カフェインが切れると、アドレナリンの分泌が低下します。
それに伴って、疲労感が増す可能性があります。
ロングライドでは、カフェインの影響がなくなりパフォーマンスが低下するかも知れません。
トレーニングから2時間経ったら、補給を多めにするなどの対策が必要です。
カフェイン耐性ができる
カフェインを日常的に摂っていると、耐性ができます。
習慣的にコーヒーを飲む人は、カフェインを摂取しても心拍数が上昇しにくくなります。
カフェインの耐性ができますが、効果がなくなる訳ではありません。
カフェイン摂取の効果を最大限にするために、重要なレースの1週間前からコーヒーを飲まなくするのも効果的です。